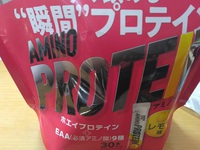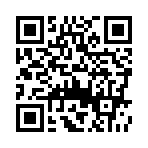2015年01月21日
内無双といえば、増位山
さっきスポーツニュースを見ていたら、大相撲の結果をやってて、栃ノ心-逸ノ城戦で出た内無双という決まり手。
とっさに増位山を思い出しました。
昭和の大相撲は決まり手も多彩でしたね。
そんな力士も多かったように思います。
栃赤城とか栃剣とか、技のデパートと形容されましたね。
あ~なつかしや・・・。(^^)
とっさに増位山を思い出しました。
昭和の大相撲は決まり手も多彩でしたね。
そんな力士も多かったように思います。
栃赤城とか栃剣とか、技のデパートと形容されましたね。
あ~なつかしや・・・。(^^)
2015年01月21日
学校の統廃合という選択肢
やっぱり教育においても費用削減が求められ、合理化が必要だということなのだろう。
小規模校の統廃合について、なんと60年ぶりに国が方針を見直したのだそうで。
その中では、通学の目安「1時間」(バスなども利用して)という基準も明確になりました。
井川から1時間以内で通える学校は、静岡市内にはありません。
静岡市内にはありませんが、川根本町には1時間以内で通える学校があります。
ただ、ここには大きな見えない壁があって、いわゆる管轄する教育事務所をまたぐことになります。
静岡市から井川に提示されている案の中にも、川根本町という選択肢は入っていません。
いま井川に求められている選択は、現状別々の場所にある小学校と中学校を合同校舎にできないか、という案です。
間違いなく、そうなっていくのでしょう。
ただ、視点を10年、20年以上先に置くと、事情がかなり異なってきます。
そもそも学校自体が存続できなくなるからです。
井川は今年で幼稚園児が0になります。
幼稚園に入園する子供の目途もたっていません。
ということは、いまのままで10年後にいまの年長さんたちが中学を卒業すると、中学生以下の子供がいなくなるということです。
あくまで、このままいくとの話ですが。
このような事情を持つ多くの地域では、廃校ではなく一時休校という措置を取るところが多いそうです。
子供が0になる→即廃校、にすると今度子供が増えたときに再び学校を始めることが相当困難になるそうです。
したがって、休校とします。
休校なら、子供が来た時点でわりとすんなり学校が再開できるそうです。
昨年末に、市の教育委員会の方々とお話しする機会がありました。
地域のひっ迫した現状や真実を分かってもらうことはかなり難しいことだと感じました。
また、行政の力が頼りとなることでも、その限界もあることも分かりました。
ある程度は家庭や地域の努力(小規模校である地域であるが故の我慢・・といったらいいか)も必要ですし、かといって義務教育に他の地域との落ち度が生じては大問題です。
当然、地域間での違いはあると思います。地域によって教育の質に差があっては問題ですが、内容が違うことはそれは地域の特色と言えます。
井川の学校も地域の個性を生かした教育をいつも行ってくれていると感じますし、部活でも全校生徒でバドミントンの団体戦のメンバーになって戦えるという小規模校特有の環境にあります。(去年から個人戦しか出られなくなりましたが・・)
それらをマイナスと捉えるのではなく、プラスと捉えて指導していくのが学校はもちろん、私たち地域の大人の役割であると考えます。
時代と共に移り変わる環境に適応しながら、地域で暮らしていかなければなりません。
ある程度の地域の小規模校を集めて統合するという事象も今後増えてくるのでしょう。
その反面、東京一極集中を避けるといった動きや、首都移転なんて話も出てきます。
やっぱ、過去にお金をかけるところを間違えていたんじゃないか、という疑問は残りますね・・。
小規模校の統廃合について、なんと60年ぶりに国が方針を見直したのだそうで。
その中では、通学の目安「1時間」(バスなども利用して)という基準も明確になりました。
井川から1時間以内で通える学校は、静岡市内にはありません。
静岡市内にはありませんが、川根本町には1時間以内で通える学校があります。
ただ、ここには大きな見えない壁があって、いわゆる管轄する教育事務所をまたぐことになります。
静岡市から井川に提示されている案の中にも、川根本町という選択肢は入っていません。
いま井川に求められている選択は、現状別々の場所にある小学校と中学校を合同校舎にできないか、という案です。
間違いなく、そうなっていくのでしょう。
ただ、視点を10年、20年以上先に置くと、事情がかなり異なってきます。
そもそも学校自体が存続できなくなるからです。
井川は今年で幼稚園児が0になります。
幼稚園に入園する子供の目途もたっていません。
ということは、いまのままで10年後にいまの年長さんたちが中学を卒業すると、中学生以下の子供がいなくなるということです。
あくまで、このままいくとの話ですが。
このような事情を持つ多くの地域では、廃校ではなく一時休校という措置を取るところが多いそうです。
子供が0になる→即廃校、にすると今度子供が増えたときに再び学校を始めることが相当困難になるそうです。
したがって、休校とします。
休校なら、子供が来た時点でわりとすんなり学校が再開できるそうです。
昨年末に、市の教育委員会の方々とお話しする機会がありました。
地域のひっ迫した現状や真実を分かってもらうことはかなり難しいことだと感じました。
また、行政の力が頼りとなることでも、その限界もあることも分かりました。
ある程度は家庭や地域の努力(小規模校である地域であるが故の我慢・・といったらいいか)も必要ですし、かといって義務教育に他の地域との落ち度が生じては大問題です。
当然、地域間での違いはあると思います。地域によって教育の質に差があっては問題ですが、内容が違うことはそれは地域の特色と言えます。
井川の学校も地域の個性を生かした教育をいつも行ってくれていると感じますし、部活でも全校生徒でバドミントンの団体戦のメンバーになって戦えるという小規模校特有の環境にあります。(去年から個人戦しか出られなくなりましたが・・)
それらをマイナスと捉えるのではなく、プラスと捉えて指導していくのが学校はもちろん、私たち地域の大人の役割であると考えます。
時代と共に移り変わる環境に適応しながら、地域で暮らしていかなければなりません。
ある程度の地域の小規模校を集めて統合するという事象も今後増えてくるのでしょう。
その反面、東京一極集中を避けるといった動きや、首都移転なんて話も出てきます。
やっぱ、過去にお金をかけるところを間違えていたんじゃないか、という疑問は残りますね・・。