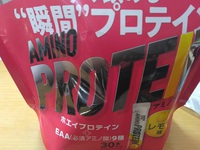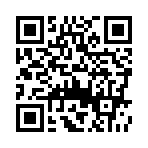2015年04月24日
部活は「体験型自由研究」
ワタクシは普段、部活は国語とか数学とかの授業とおなじという思いで指導にあたっています。
でもそういう言い方では、生徒たちは部活動をたぶん好きにはなれないでしょう。(^^;
生徒の視点からすれば、部活は「体験型自由研究」なんだと思います。
しかも1年生の入部から3年生の中体連までの2年数カ月の長い時間をかけ、自分がどれほど成長するかを試す研究です。
やっつけでやる夏休みの自由研究はやらされ感満載でしょうが・・(^^;
自分自身がテーマとなっている研究が終わるとき、どれほどの成長があったのかってことを自分で分かれば、すなわちそれは自己肯定感が身につくことになるんだな。(^^)
でもそういう言い方では、生徒たちは部活動をたぶん好きにはなれないでしょう。(^^;
生徒の視点からすれば、部活は「体験型自由研究」なんだと思います。
しかも1年生の入部から3年生の中体連までの2年数カ月の長い時間をかけ、自分がどれほど成長するかを試す研究です。
やっつけでやる夏休みの自由研究はやらされ感満載でしょうが・・(^^;
自分自身がテーマとなっている研究が終わるとき、どれほどの成長があったのかってことを自分で分かれば、すなわちそれは自己肯定感が身につくことになるんだな。(^^)
2015年04月24日
井川中バドミントン部
中学生になると、部活動という教育活動があります。
中学校の学習指導要領では、「生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動・・(以下略)」とあります。
ワタクシもそうでしたが、街なかの大きな学校では「何部に入るか?」選択できます。
井川のような小規模校の多くは、選択できません。
井川中の部活動がバドミントン部だけになって20年以上が経過しました。
この間、やむを得ない事情があってできなかった生徒は若干いましたが、ほぼ全員が井川中でバドミントン部を経験しています。
この中には、明らかに運動が苦手な子や、他の種目が好きだった子などが多くいましたが、みんなよくやり切ったと思います。
このように、部活の選択肢がない中でもみんながやり切った理由の一つに、地域の環境があります。
井川では小学生が行う少年団活動を長く継続しています。そこで指導している人たちの中に、中学校の部活にも関わっている人が何人かいます。
部活指導員だけが関わっているのではなく、多くの地域の人たちに支えられています。
そんな中で育つ子供たちは、自然と「井川中に入ったら、バドミントンをやるんだ!」という意識が芽生えます。
でも、少年団活動でバドミントンをやっていたわけではありません。小学生のバドミントン教室を行うようになった歴史は、まだ10年程度です。
なぜ、子供たちにこのような意識が芽生えるのか?それは、小規模校の子供たちにとって経験することが少ない「団体行動」の必要性を考えた指導を行ってきたからだと考えます。
種目は違っても、団体の中で自分はどうあるべきか、どのように行動すればよいか、が身についたのだと思います。
さらには、小規模校だからこそ、小学生が中学生と接する機会が家庭や地域の中で多いということもあります。
小学生の教室を始めたばかりの時、自分たちの練習よりも、隣のコートで試合をやっている中学生の姿をしきりに見ている子が多くいました。
要は身近なお兄さんお姉さんたちがカッコいい!のです。
だから、自分もこうなりたい!と。
良い伝統はずっと引き継がれています。
でも、そのようにいかないケースだってあるわけです。
こちらの思う「既定路線」に乗っていない子がいる場合どうしたらいいのか?
人数が減って団体戦ができなくなりました。団体戦があるからこそバドミントン部は楽しいと思ってきたワタクシにとっても、かなり凹む出来事です。
団体戦ができない子供たちはかわいそうだなぁと思います。
今日、今年度の部活動について学校と話し合いがあります。
いつも先輩方が作り上げてきた井川中バドミントン部の原点を忘れずに!と思っていますが、今の時代になったからこその新たな課題には、いまいるワタクシたちがしっかりと答えを導き出し、後継者に引き継がなければならないと考えています。
中学校の学習指導要領では、「生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動・・(以下略)」とあります。
ワタクシもそうでしたが、街なかの大きな学校では「何部に入るか?」選択できます。
井川のような小規模校の多くは、選択できません。
井川中の部活動がバドミントン部だけになって20年以上が経過しました。
この間、やむを得ない事情があってできなかった生徒は若干いましたが、ほぼ全員が井川中でバドミントン部を経験しています。
この中には、明らかに運動が苦手な子や、他の種目が好きだった子などが多くいましたが、みんなよくやり切ったと思います。
このように、部活の選択肢がない中でもみんながやり切った理由の一つに、地域の環境があります。
井川では小学生が行う少年団活動を長く継続しています。そこで指導している人たちの中に、中学校の部活にも関わっている人が何人かいます。
部活指導員だけが関わっているのではなく、多くの地域の人たちに支えられています。
そんな中で育つ子供たちは、自然と「井川中に入ったら、バドミントンをやるんだ!」という意識が芽生えます。
でも、少年団活動でバドミントンをやっていたわけではありません。小学生のバドミントン教室を行うようになった歴史は、まだ10年程度です。
なぜ、子供たちにこのような意識が芽生えるのか?それは、小規模校の子供たちにとって経験することが少ない「団体行動」の必要性を考えた指導を行ってきたからだと考えます。
種目は違っても、団体の中で自分はどうあるべきか、どのように行動すればよいか、が身についたのだと思います。
さらには、小規模校だからこそ、小学生が中学生と接する機会が家庭や地域の中で多いということもあります。
小学生の教室を始めたばかりの時、自分たちの練習よりも、隣のコートで試合をやっている中学生の姿をしきりに見ている子が多くいました。
要は身近なお兄さんお姉さんたちがカッコいい!のです。
だから、自分もこうなりたい!と。
良い伝統はずっと引き継がれています。
でも、そのようにいかないケースだってあるわけです。
こちらの思う「既定路線」に乗っていない子がいる場合どうしたらいいのか?
人数が減って団体戦ができなくなりました。団体戦があるからこそバドミントン部は楽しいと思ってきたワタクシにとっても、かなり凹む出来事です。
団体戦ができない子供たちはかわいそうだなぁと思います。
今日、今年度の部活動について学校と話し合いがあります。
いつも先輩方が作り上げてきた井川中バドミントン部の原点を忘れずに!と思っていますが、今の時代になったからこその新たな課題には、いまいるワタクシたちがしっかりと答えを導き出し、後継者に引き継がなければならないと考えています。