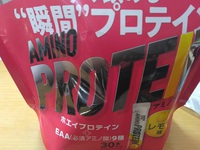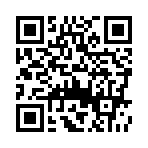2015年08月17日
悪い流れを引き寄せない、勝利への近道
夏の甲子園、高校野球も最も面白いと言われるベスト8の対決、準々決勝を迎えています。
これ、なんで面白いのかってよく理由は分かりませんが、一つに一日で4試合観られる中で必ずその中に優勝チームがいるというのもあったんじゃないかな~。
で、それにしても高校野球は試合展開が早い!
試合時間が3時間を超えることなんて稀で、当初の試合開始予定時刻も前の試合の開始時間から2時間半後に設定されています。
そんな早い試合展開であっても、試合の行方を左右するプレーの流れというものは存在するわけです。
一番悪い流れは、ミス、エラー、敬遠ではないフォアボールが出たとき。
これらは、自チームにとっては負けパターン。相手のこれらを予測することは不可能なので、そういった隙をついてすかさず得点したり、失点を防いだりしながら勝利に近付いていきます。
ただ逆に言っても勝ちパターンではないところが、スポーツの難しいところ。単にエラーが出た、フォアボールが出ただけでは得点できないわけですが、「少ない安打で得点につながる確率が高まった」というのがより正確な表現なんでしょうか。
野球は、最低0本の安打でも得点はできます。逆に4本の安打を打てば、最低1点は入ります。
この確率を考えれば、エラーやフォアボールが得点につながりやすいという理屈が納得できると思います。
ゆえに、結果試合の勝敗につながってくるわけで。
さて、これをバドミントンで考えてもさほど大きな違いはありません。
中学生の試合を観ていると、自らのショットが決まって得点が入るよりも、相手のミスで入る得点のほうが多い試合があります。
もしも、相手が一本のミスもしなかったならば、1ゲームあたり21本のショットを決めなければなりません。
仮に、相手が10本のミスをしてくれれば、自らが決めるショットは11本で済みます。
どちらが楽な試合展開かは一目瞭然です。
レベルが上がってくればくるほど、ミスの少ないラリーが展開され、自分が決めたいと思って打ったショットでポイントが取れる回数は少なくなります。
だから、バドミントンにも勝ちパターンなどはなく、いかに細かなミスを減らせるかが勝利への近道。
21点を先に取るまでにも様々な試合展開がありますが、結果負けたときには素直に相手の実力を認め「自分の実力が足りなかった」と言えるようなところまで、自分の練習の成果に自信を持ってもらいたいなと思っています。
これ、なんで面白いのかってよく理由は分かりませんが、一つに一日で4試合観られる中で必ずその中に優勝チームがいるというのもあったんじゃないかな~。
で、それにしても高校野球は試合展開が早い!
試合時間が3時間を超えることなんて稀で、当初の試合開始予定時刻も前の試合の開始時間から2時間半後に設定されています。
そんな早い試合展開であっても、試合の行方を左右するプレーの流れというものは存在するわけです。
一番悪い流れは、ミス、エラー、敬遠ではないフォアボールが出たとき。
これらは、自チームにとっては負けパターン。相手のこれらを予測することは不可能なので、そういった隙をついてすかさず得点したり、失点を防いだりしながら勝利に近付いていきます。
ただ逆に言っても勝ちパターンではないところが、スポーツの難しいところ。単にエラーが出た、フォアボールが出ただけでは得点できないわけですが、「少ない安打で得点につながる確率が高まった」というのがより正確な表現なんでしょうか。
野球は、最低0本の安打でも得点はできます。逆に4本の安打を打てば、最低1点は入ります。
この確率を考えれば、エラーやフォアボールが得点につながりやすいという理屈が納得できると思います。
ゆえに、結果試合の勝敗につながってくるわけで。
さて、これをバドミントンで考えてもさほど大きな違いはありません。
中学生の試合を観ていると、自らのショットが決まって得点が入るよりも、相手のミスで入る得点のほうが多い試合があります。
もしも、相手が一本のミスもしなかったならば、1ゲームあたり21本のショットを決めなければなりません。
仮に、相手が10本のミスをしてくれれば、自らが決めるショットは11本で済みます。
どちらが楽な試合展開かは一目瞭然です。
レベルが上がってくればくるほど、ミスの少ないラリーが展開され、自分が決めたいと思って打ったショットでポイントが取れる回数は少なくなります。
だから、バドミントンにも勝ちパターンなどはなく、いかに細かなミスを減らせるかが勝利への近道。
21点を先に取るまでにも様々な試合展開がありますが、結果負けたときには素直に相手の実力を認め「自分の実力が足りなかった」と言えるようなところまで、自分の練習の成果に自信を持ってもらいたいなと思っています。