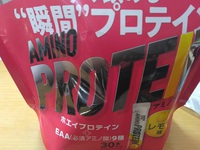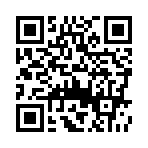2014年12月10日
互恵関係
日本の外交問題でよく耳にするこの「互恵関係」という言葉。
お互いが恩恵を受け、与える関係という意味では、今どきの言葉では「win win」の関係ともいえるのでしょうか。
さて、先日ISCのことや地域の子供たちのことなど話を聞きたいということで、ある大学生の訪問を受けました。
彼は井川に興味を持って、これまでにも何回か訪れてくれていました。
話をしていく中で、ワタクシ自身初心に立ち返る場面や、忘れかけてたことを思い出すきっかけとなることもあり、とても有意義な時間を過ごしました。
話の最後のほうで、ワタクシは彼のある質問にハッとしました。
「ISCの活動で、子供たちから大人へ与えたいい影響はありますか。」
答えに窮しました。
子ども達が地域の大人たちと活動する中で、挨拶やマナーなどいわゆる社会性を身に付けさせることは普段の指導から心掛けてきたことであり、それが中学を卒業するとともに井川を巣立っていく子供たちのために、ISCが一定の役割を果たしているのではないだろうかという思いはありました。
しかし、その逆のことについては全く頭にありませんでした。
ISCの活動の中でも大人と子供が同じ時間、同じ場所で行うのはバドミントンです。
そういえば、昔々ワタクシが井川に来てバドミントンを始めたばかりの頃、とても上手な中学生のプレーを見て「すごいな~!」と思い、そのうち「いっしょに試合できるかな~」、そして「勝ちたい!」と思うようになりました。
そういった意味では、子供たちから刺激を受け、自分自身のスキルアップにつながったという影響はあったな~という話をしました。
しかしながら、ワタクシ自身の中で、実は表立っては見えないけど何か別に好影響はあるのではなかろうか・・という思いが残りました。
でもすぐには思い浮かびませんでした。
あれから4日・・。
ようやくモヤモヤの正体が判明しました。
答えは「ISCを続けていること」なんです。
つまり、私たちは子供たちが活動する場所を作ることで、将来帰ってくる場所も作ることになるのです。子供たちは大人になって帰ってきて、昔自分が大人の人にバドミントンを教えてもらったように、今度は大人になった自分が子供たちに教えることができる。
今いる大人たちはそんな環境をつくることで、自分たちが井川でよりよく暮らすための働きができる。地域で子供が育てられる環境をつくることは、地域が存続していけるということにつながるのです。
いま井川に戻ってきた30歳前後の若い人たちの中には、彼らが中学生の頃にバドミントンを一緒にやった仲間がいます。Uターンはできずとも、長い休みなどで井川に戻ってきて体育館にバドミントンをやりに来てくれる人たちも多くいます。
小学生のころにやったサッカーでは、毎年正月に「初蹴り」を行っていて、今年の正月もたくさん集まってくれました。
このような循環が井川の地域では出来ています。
明らかに恩恵のベクトルが働いているというのではないけれど、あくまでも日々の活動の中で行われ、且つ長い期間をかけて子どもと大人(地域と言ってもいい)へも恩恵が還元されているというのが、井川の中におけるISCの役割であり、大人と子供の関係であると思いました。
過疎地で、今後も人口減少が顕著であろう井川を少しでも長く暮らせる地域にするため、ISCができる役割は担っていきたいと改めて実感しました。
こんな大事なことがすぐに答えられなかったことに恥ずかしさがのこるわけですが、改めて考えるきっかけを与えてくれた大学生には、感謝の気持ちでいっぱいであります。
ありがとう!(m_ _m)
お互いが恩恵を受け、与える関係という意味では、今どきの言葉では「win win」の関係ともいえるのでしょうか。
さて、先日ISCのことや地域の子供たちのことなど話を聞きたいということで、ある大学生の訪問を受けました。
彼は井川に興味を持って、これまでにも何回か訪れてくれていました。
話をしていく中で、ワタクシ自身初心に立ち返る場面や、忘れかけてたことを思い出すきっかけとなることもあり、とても有意義な時間を過ごしました。
話の最後のほうで、ワタクシは彼のある質問にハッとしました。
「ISCの活動で、子供たちから大人へ与えたいい影響はありますか。」
答えに窮しました。
子ども達が地域の大人たちと活動する中で、挨拶やマナーなどいわゆる社会性を身に付けさせることは普段の指導から心掛けてきたことであり、それが中学を卒業するとともに井川を巣立っていく子供たちのために、ISCが一定の役割を果たしているのではないだろうかという思いはありました。
しかし、その逆のことについては全く頭にありませんでした。
ISCの活動の中でも大人と子供が同じ時間、同じ場所で行うのはバドミントンです。
そういえば、昔々ワタクシが井川に来てバドミントンを始めたばかりの頃、とても上手な中学生のプレーを見て「すごいな~!」と思い、そのうち「いっしょに試合できるかな~」、そして「勝ちたい!」と思うようになりました。
そういった意味では、子供たちから刺激を受け、自分自身のスキルアップにつながったという影響はあったな~という話をしました。
しかしながら、ワタクシ自身の中で、実は表立っては見えないけど何か別に好影響はあるのではなかろうか・・という思いが残りました。
でもすぐには思い浮かびませんでした。
あれから4日・・。
ようやくモヤモヤの正体が判明しました。
答えは「ISCを続けていること」なんです。
つまり、私たちは子供たちが活動する場所を作ることで、将来帰ってくる場所も作ることになるのです。子供たちは大人になって帰ってきて、昔自分が大人の人にバドミントンを教えてもらったように、今度は大人になった自分が子供たちに教えることができる。
今いる大人たちはそんな環境をつくることで、自分たちが井川でよりよく暮らすための働きができる。地域で子供が育てられる環境をつくることは、地域が存続していけるということにつながるのです。
いま井川に戻ってきた30歳前後の若い人たちの中には、彼らが中学生の頃にバドミントンを一緒にやった仲間がいます。Uターンはできずとも、長い休みなどで井川に戻ってきて体育館にバドミントンをやりに来てくれる人たちも多くいます。
小学生のころにやったサッカーでは、毎年正月に「初蹴り」を行っていて、今年の正月もたくさん集まってくれました。
このような循環が井川の地域では出来ています。
明らかに恩恵のベクトルが働いているというのではないけれど、あくまでも日々の活動の中で行われ、且つ長い期間をかけて子どもと大人(地域と言ってもいい)へも恩恵が還元されているというのが、井川の中におけるISCの役割であり、大人と子供の関係であると思いました。
過疎地で、今後も人口減少が顕著であろう井川を少しでも長く暮らせる地域にするため、ISCができる役割は担っていきたいと改めて実感しました。
こんな大事なことがすぐに答えられなかったことに恥ずかしさがのこるわけですが、改めて考えるきっかけを与えてくれた大学生には、感謝の気持ちでいっぱいであります。
ありがとう!(m_ _m)